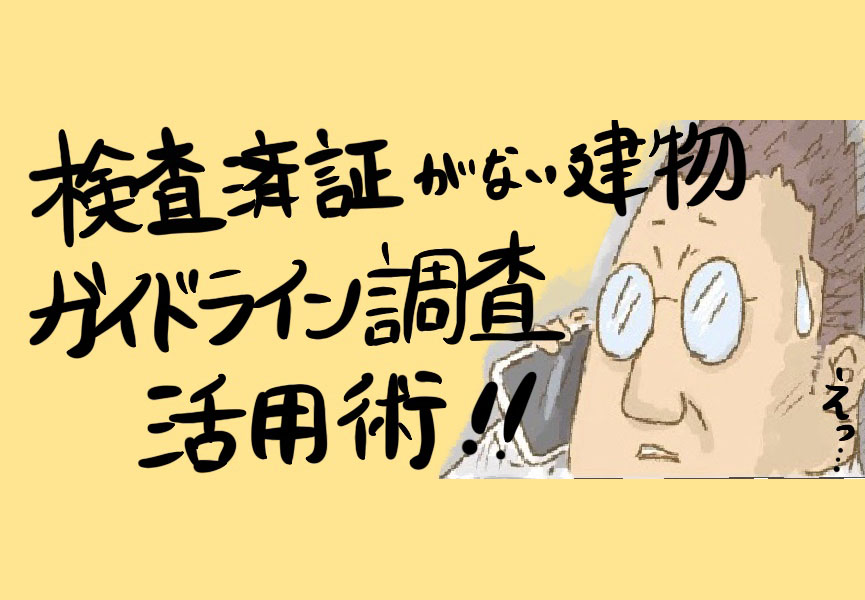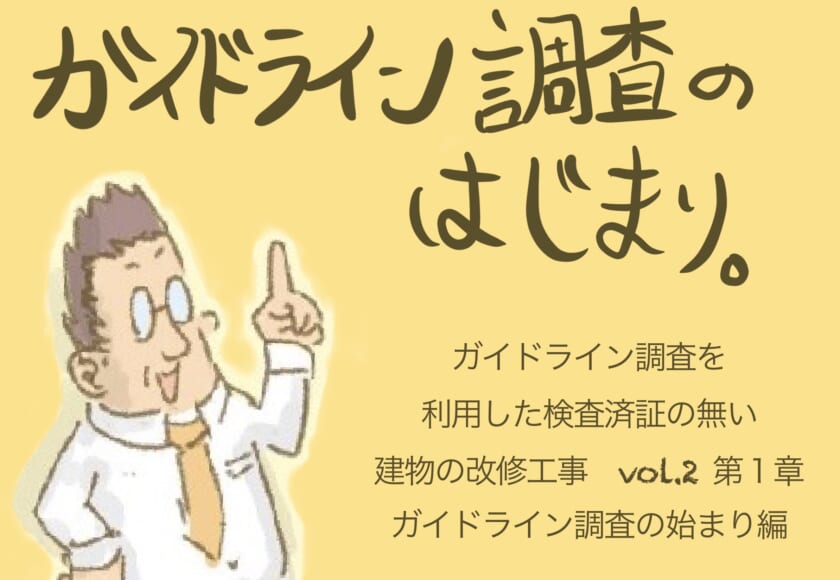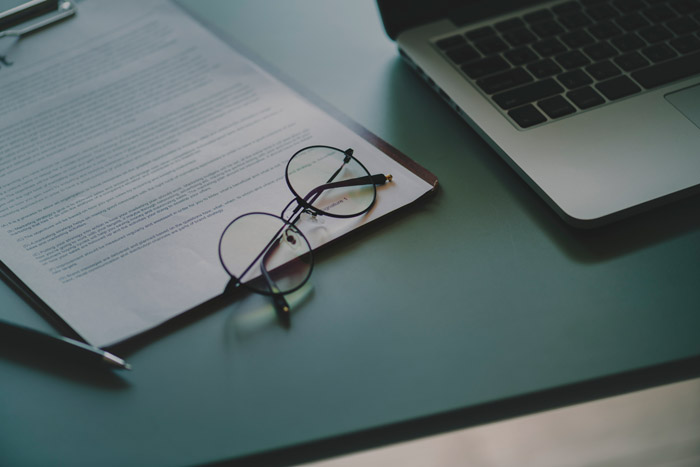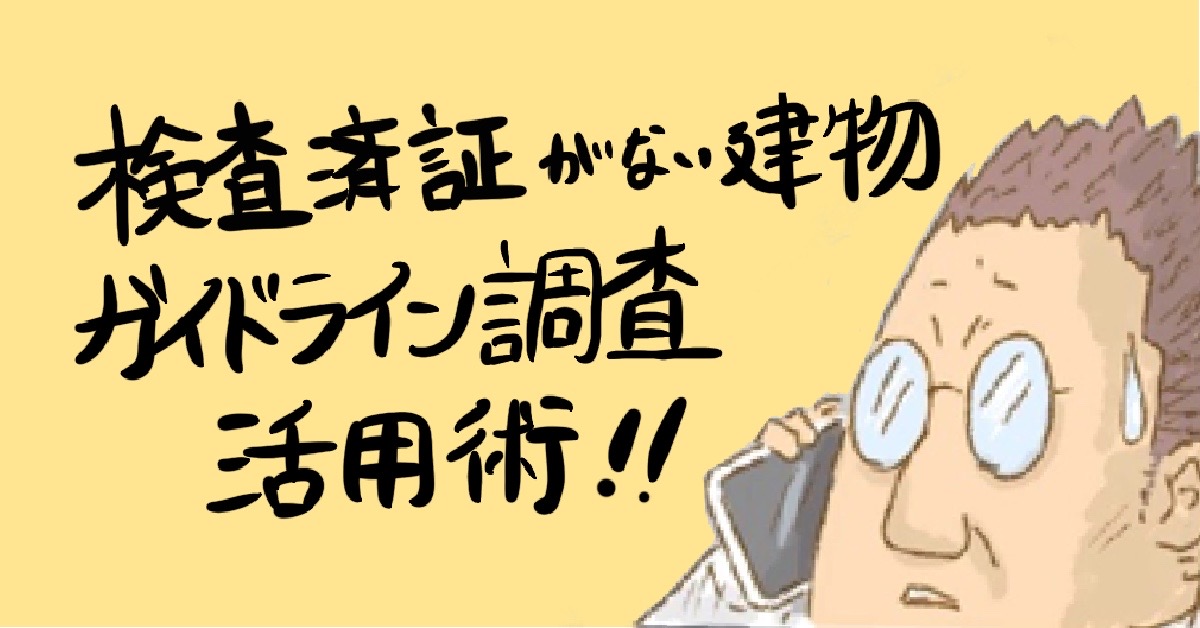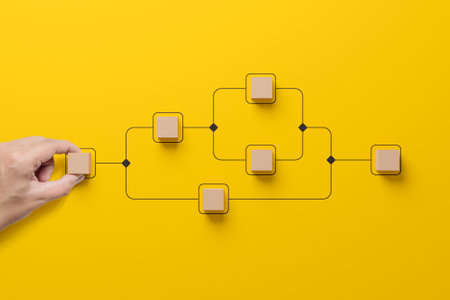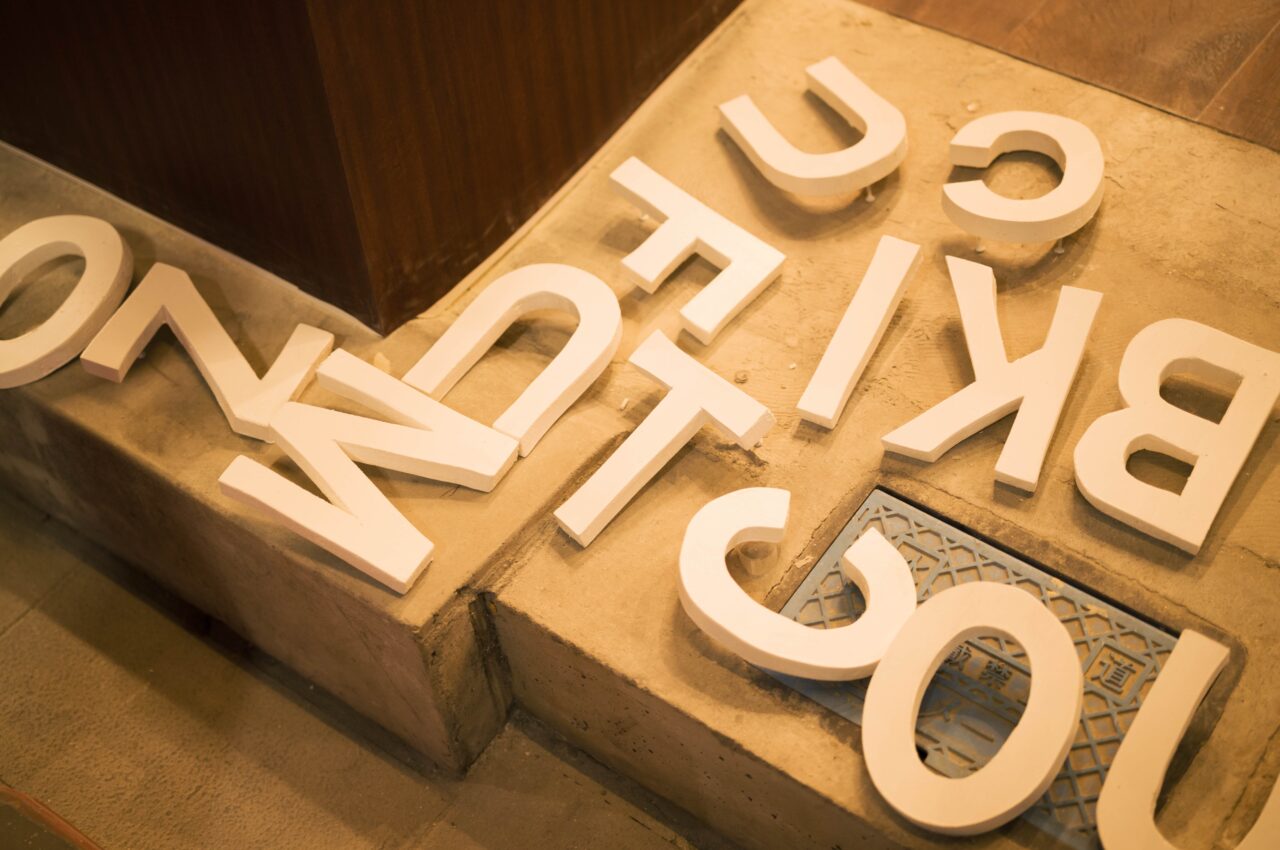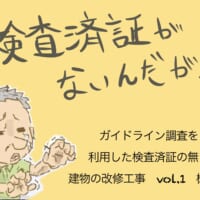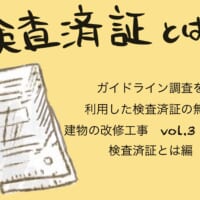ガイドライン調査とは?
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」により、国土交通省へ届出を行った指定確認検査機関等が実施する法適合状況調査のことです。
1999年までの完了検査率
1999年までに建てられた建築物に関しては、半数以上も検査済証が発効されていないという現実があります。現在(令和4年)換算だと、築23年以上の建物に関しては、半数以上の確率で検査済証が無いということになります。
下記が、国土交通省のサイトにも掲載されているグラフになるのですが、 当時は38%の検査率です。

*「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を 活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン 」から抜粋
検査済証が無い建物だと、改修工事が・・・
- 用途変更
- エレベーターの設置
- 増改築
- 大規模改修や大規模模様替
検査済証が無いと、主に上記のような改修工事を行うことが難しくなります。上記のような改修工事は、工事を始めるにあたり申請を伴う工事になるのですが、申請の際に検査済証の添付を求められるからです。
また、売買や当該建物に関する工事などの銀行等融資が受けづらいというデメリットもあるようです。
検査済証ない建物はどうするのか
解体などして建替えるという選択肢もあります。ただ、今までのスクラップ&ビルドのように、壊して新しいものを建てるという方法だけでなく、今後も既存ストックの活用(既存建物を活かして再利用する)が求められていく時世でもあり、SDGsの観点からも増えていく選択肢だと思います。
そこでどうしても問題になるのが、検査済証です。無い理由で上記のような改修工事ができないことは、既存ストックの再利用を進めていく上での、ボトルネックになってしまいます。
ガイドライン調査が解決手段の一つに
そのような背景もあり平成26年に国土交通省から「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」通称、「ガイドライン調査」が策定されました。
*以前は、検査済証が無い建物に対して、法適合調査などを行い、特定行政庁へ報告をするという方法はありました。(12条5号報告) ただ、建築基準法で定められいるだけで、具体的な方法が決められているわけではありませんでした。
ガイドライン調査においては、国から指定された民間の指定確認検査機関にて、調査を行うことが可能になりました。是非の判断は勿論あり、調査項目のボリュームもかなりのものにはなりますが、相談確認の上進めていくことができます。具体的な内容のご紹介は、次回以降の投稿になっていきますが、ガイドライン調査を利用して、既存ストックの再利用、工事の目的が達成できなく断念されていた方々の解決になる一手になるのではないでしょうか。
次回に続く・・・
下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。
日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。
必要書類・費用予測等などもご紹介します。